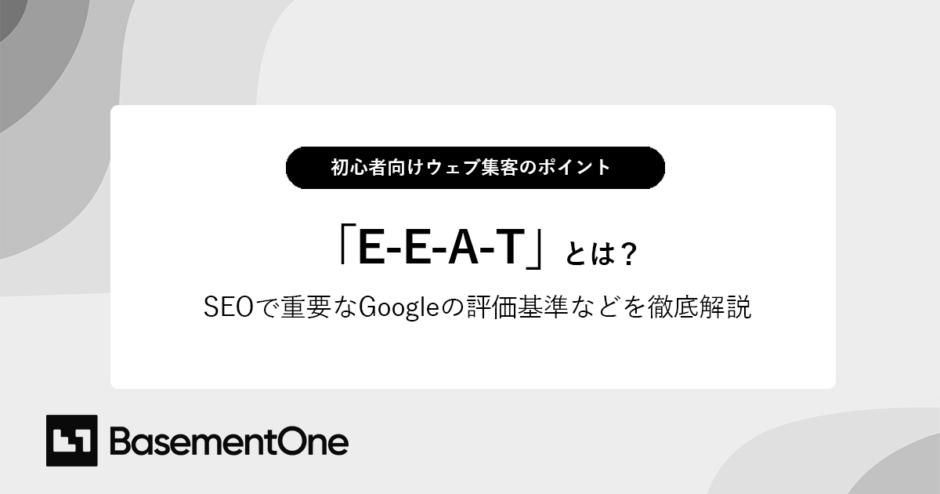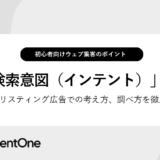SEOにおいて2018年以降重要視され始めた「E-A-T」という概念は、「E-E-A-T」という単語にアップデートされ、重要視される要素となっています。
弊社でも先日「上位10位内にランクインしていたキーワードが30位以降や100位圏外まで検索順位が低下してしまった」とお客様よりご相談を受け原因調査を実施したところ、E-E-A-Tが影響を及ぼしていることが判明しました。
2023年11月に実施されたGoogleのコアアルゴリズムアップデートにて、Googleがウェブサイトに期待する「専門性」に変化があり、記事コンテンツの評価が下がってしまったという事象でした。現在、記事のリライト、追加記事作成を行うなど対応を急いでいるところです。
本記事では、E-E-A-Tとは何か、Googleが重要視している理由を解説し、サイト運営者として実施すべき具体的な9つの対策方法などを解説しています。
最後まで読んだ方がご自身でE-E-A-T対策を行えることをゴールに執筆していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそもE-E-A-Tとは何なのか?
Googleの検索品質評価ガイドラインによると、E-E-A-Tとは
・Experience(経験)
・Expertise(専門性)
・Authoritativeness(権威性)
・Trust(信頼性)
の4つの要素を指しています。
Googleがサイトやコンテンツの品質を測り評価するために、
・サイトや記事の専門性や権威性の有無
・実際の経験が反映されているのか
・信頼に足るサイトなのか
といった点を重要視するようになっています。

E-E-A-Tが重要視されている理由
ブログやSNSなどが普及し、個人でも情報を容易に発信できるようになったいま、ユーザーがどの情報を信じるべきか判断するのが難しくなってきています。
また、生成AIによる記事コンテンツ生成が可能となったため、
・Googleを検索しても、生成AIに聞くのと同じような情報ばかり出てくる
・Googleを利用する理由付けが必要
このような問題をGoogleは経験/専門性/権威性/信頼性の高い=E-E-A-Tが優れているサイトを上位表示することで、ユーザーに信頼できる情報を素早く届けることで解決を図っているようです。
E-E-A-Tを高めることが「Googleは信頼できる検索エンジンだ!」という信頼獲得に繋がり、ユーザーがGoogleを使う理由となるため、GoogleはE-E-A-Tによる評価を重要視するようになっていると考えられます。
ここからは、E-E-A-Tの各要素について説明していきます。
E-E-A-Tの4要素
経験(Experience)
E-A-TとE-E-A-Tの違い
2022年12月、Googleは品質評価ガイドラインでE-A-Tに「経験(Experience)」を加え、「E-E-A-T(ダブルイーエーティ)」に更新したことを発表しました。
つまり、「コンテンツに実体験・経験を交える方が信頼に値する情報であるとGoogleは評価をするよ」という意思表示と考えられます。
このたび、検索結果の評価を改善するために、E-A-T に E(経験)を追加しました。つまり、実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。状況によっては、そのトピックに関連して実体験をもつ人が作成したコンテンツが最も高く評価される場合もあります。
Google 検索セントラル ブログ
E-E-A-T以前の記事コンテンツではターゲットキーワードの検索上位10位に表示される記事をいい感じに流用すれば、実際に知見や体験がなくても記事をつくることができる状況でした。
このようないわゆる「こだつ記事」をGoogleはユーザーのためにならないと判断したのかなと推察しています。
品質評価ガイドラインには具体例として、確定申告に関するコンテンツ例が記載されていました。
たとえば、確定申告書の正しい記入方法を知りたいときには、会計の専門家が作成したコンテンツを参照したいでしょう。一方で、確定申告ソフトの評価を知りたいのであれば、その種のサービスを体験した人たちが集まるフォーラムの議論など、別の情報を探すのではないでしょうか。
Google検索セントラル
専門性(Expertise)
専門性(Expertise)とは、著者やサイト全体が特定の分野においての専門的な情報を有しているか、という指標です。
特定の分野について専門的であるほうが、ユーザーの抱える悩みや問題に答えられる確率が上がるため、Googleに高く評価されます。
サイト全体のテーマが統一されており、サイトにそのテーマに関する情報が充実していることや、コンテンツの著者のプロフィールが公開されており、専門的な知識を有していることがわかることが重要です。
下記、3点がポイントと考えられます。
- サイト全体のテーマが統一されている
- 著者のプロフィールがわかる
- 著者に専門性があることがわかる
権威性(Authoritativeness)
権威性(Authoritativeness)とは、メインコンテンツや著者、サイト全体について、第三者から信頼をおけると見なされているか、という指標です。
説得力とそれを裏付ける権威性を持っている方がGoogleに高く評価されます。
外部からどう評価されているかを測る指標であるため、サイト自体が言及されていたり(サイテーションを獲得できていたり)、業界で権威のあるサイトから被リンクを受けていたりすることが重要と考えられます。
※権威性の高いサイトの被リンク例
- 政府系ドメイン
- 社会的地位が高い団体のドメイン
- ドメインランクの高いドメイン
また、そのサイト(提供サービス)がきちんと認知され、検索者が増える=と指名検索が増加することも権威性に繋がるのではないかと推察しています。
※今後作成予定の関連記事:「指名検索の重要性」
信頼性(Trust)
信頼性は経験/専門性/権威性の上に成立する
信頼性(Trust)とは、メインコンテンツや著者、サイト全体について信頼性があるか、という指標です。
信頼性、透明性、正確性などがあり、ユーザーにとって信頼できると判断されている方がGoogleに高く評価されます。
E-A-Tの時代には各要素に上下関係はなく並列関係でしたが、更新されたガイドラインでは「信頼性(Trust)」を最も重要な要素として上位に位置付けているようです。※下図参照

どんなに経験があり、専門的で権威性があるように見えても、信頼性が乏しいページはE-E-A-Tが低いと見なされます。
運営者情報、サイトのポリシーなどを詳しく記載することや、ウェブサイトをSSL化し安全性を高めることが重要です。
下記がポイントになると考えています。
- 運営者情報が公開されている
- 発信している情報のソースが明示されている
- サイトのポリシーが明示されている
- ウェブサイトがSSL化されている
E-E-A-TとYMYLの関係性
YMYLとは「Your Money or Your Life」の略で、直訳すると「あなたのお金と人生」となります。
YMYLに含まれるジャンルは、もし間違っているとコンテンツの閲覧者に重大な損害を与えてしまうため、Googleが評価を厳格にしており、E-E-A-Tも特に重視されます。
YMYLのテーマ・カテゴリの代表例
- 医療・健康
- 金融・投資
- 法律
- 政治
- ショッピング
※今後作成予定の関連記事:「YMYLの重要性」
E-E-A-Tを高める方法(E-E-A-T対策)
ここからは、E-E-A-Tを高める具体的な対策方法について紹介します。是非ご自身のサイトにも生かしてみてください。
ウェブサイトを専門カテゴリ、ジャンルに特化させる(専門性)
専門性を高めるためには、ウェブサイトのテーマやジャンルを絞ることが重要です。
例えば、医療、美容、不動産、など多岐にわたる情報を発信するサイトよりも、医療なら医療、美容なら美容、というように情報を絞ったサイトのほうが、ユーザーにもGoogleにも「専門性が高い」と評価されやすくなります
専門家や経験者の一次情報を記載する(経験、専門性)
一次情報とは、自身が直接体験したり調査をしたりして得た情報のことです。
例えば、確定申告のやり方に関する記事であれば、専門的な知識を持つ税理士や、個人事業主で何度も確定申告をした経験を持っている人が書いた記事の方が、そうでない記事よりも良いコンテンツだと評価されます。
専門家や体験者にヒアリングをする、アンケートを取って顧客の声を集めるなどして、一次情報をコンテンツに反映させることを心がけましょう。
サイト運営者、コンテンツの著者情報を明記する(権威性、信頼性)
検索エンジンは「誰が発信しているのか」を判断するために「著者名」や「運営者名」などの情報を見ています。そのため、サイト内にそのような情報を記載したページを追加したり、記事内に明記したりしましょう。
運営者、運営する会社の住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先を記載すると信頼性が高まります。
Googleビジネスプロフィールに登録する(権威性、信頼性)
Googleビジネスプロフィールとは、Google検索やGoogleマップ検索などに会社情報や店舗情報などを表示し、管理することができるGoogleの無料ツールです。
Googleビジネスプロフィールに登録し、運営情報をGoogleにもユーザーにも開示すれば、権威性や信頼性の獲得に繋がります。
GoogleはWebサイトだけでなく、あらゆる情報を蓄積して評価していることを理解しましょう。
指名検索が増えるようブランディングを行い認知度を上げる(権威性)
指名検索とは、企業名、製品名、人物名などを含んだ検索のことです。
例えば、弊社であれば、「BASEMENT ONE」「BASEMENT ONE WEB制作」などが当てはまります。
指名検索を多く獲得するサイトほど、認知度が高く、ユーザーにとって有益な情報を与えていると評価されます。
質の高い被リンクを多く獲得する(権威性)
質の高い被リンクを多く獲得することは権威性を高めるSEO対策として非常に有効です。
質の高い被リンクとは、以下のようなものです。
- 関連性の高いサイトからのリンク
- Googleからすでに権威性が高いと評価されているWEBサイトからのリンク
例えば、美容系のブログサイトであれば、大手美容クリニックなど関連性も高く、ドメインパワーも強いサイトからリンクを貼ってもらえると効果があります。
サイテーションを獲得する(権威性)
サイテーションとは「引用・言及」という意味で、サイトに関する情報が他のサイトやSNSで言及されることを指します。
これは、リンクが貼られていなくても、Webサイトの名前や著者の名前などが記載されていれば効果があります。
SNSを運用してファンを獲得し商品のことを紹介してくれるユーザーを増やす、外部メディア登録して自社の情報を掲載してもらう、などの方法があります。
前述の通り、GoogleはWebサイトのみならず、あらゆる情報を蓄積していることを理解しましょう。
引用は公的機関から行い、出典元を表記する(信頼性)
コンテンツの質は、信頼性の高いサイトを参考に作成しているかに依存すると言われています。
例えば、SEOに関する記事を書くときに、個人のサイトから引用している場合と、Googleの品質評価ガイドラインから引用している場合とでは、後者の方が信頼できる情報と言えます。
信頼性の高い情報、できれば公的機関の情報を引用し、その引用元を表記するようにしましょう。
最新の情報にアップデートする(信頼性)
Googleはフレッシュネス(情報の鮮度)を重視しています。特にニュースや流行に関するコンテンツは、古い情報だと役に立たない場合が多く、最新の情報が優遇される傾向があります。
公開済みのページも、常に情報を最新にメンテナンスし、信頼性を高めることが重要です。
まとめ:E-E-A-Tを考慮して、サイトの品質を高めよう
本記事ではSEO対策におけるE-E-A-Tの定義や対策方法について詳しくご紹介してきました。
近年のSEOにおいてE-E-A-Tは重要度を増しており、Webマーケティング担当の方は常に意識しておくことが大切です。
E-E-A-Tを高めるのには時間がかかり、地道な作業も多いですが、Googleからも、そしてユーザーからも高い評価を得るためには必要不可欠な対策です。
最後に、記事を読んでも対策を講じる時間を取ることができない、まず何から始めたらいいかわからない、そんな方に弊社では無料相談を行っています。
ご希望の方は下記よりお申込みをしてみてください。